この一冊
『シベリア抑留―スターリン独裁下、「収容所群島」の実像』(富田武著 中公新書、2016.12)
「人的賠償」名目にした報復の実態を解明
関東学院大学経済学部講師 島田 顕
本書は、シベリア抑留の啓蒙書であると同時に本格的な研究書でもある。著者は、長年にわたり、ソヴェト国家体制の研究、さらに日ソ関係の歴史を研究してきた。それらの成果が注ぎ込まれたのが著者のシベリア抑留研究であり、その集大成が本書なのである。
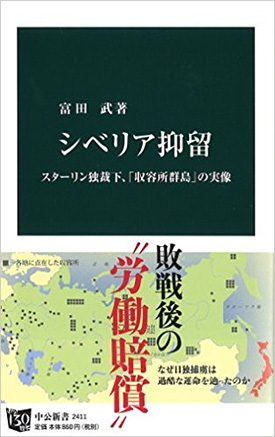
シベリア抑留とは、第二次世界大戦後に満州等にいた60万人以上の軍人、民間人が武装解除後、ソ連軍に連行され、旧ソ連諸国のほぼ全域、シベリア、ウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタンや、モンゴルにおいて強制労働に従事させられたことを指す。いわゆる「シベリア三重苦」(飢えと寒さと重労働)により6万人以上が亡くなった。
本書は、まず抑留の原点であるソ連国内の矯正労働に焦点を当てた。ロシア革命後の反革命分子の矯正を行うための施設が収容所であり、囚人達による労働力が五カ年計画として知られる重工業・インフラ整備の重点的プロジェクトに動員された。つまり、収容所の不払い労働に依存する経済システムである「ラーゲリ経済」によって成り立っていたのがソ連国家だった。次第に矯正収容所の経済的効果はなくなり、行き詰まりを見せていたが、システムは継続された。効率を上げようとして作業ノルマが引き上げられたことにより、作業がきつくなり、「水増し報告」と「見せかけの労働」が横行。収容所内部では囚人同士の生存競争、つまり「人間が人間に対して狼となる状態」が繰り広げられていた。そしてこのような状態は戦後の捕虜収容所にも共通していたといえる。
第二次世界大戦勃発に伴うソ連軍のポーランド侵攻により、ソ連は大量のポーランド人捕虜を獲得することになり、8か所の捕虜収容所の開設が指示された。本書は、ジュネーヴ条約の捕虜と抑留の違いを示し、ソ連の捕虜に対する待遇はジュネーヴ条約を無視したものだったことを明らかにした。ソ連では、捕虜収容所は軍の後方部門が管轄せず、矯正収容所を管轄し、巨大建設プロジェクトをリードしてきた内務人民委員部(内務省)が管轄するようになる。矯正収容所と捕虜収容所は、まさに経験も処遇も同じ「双生児」だったことを本書は強調する。
シベリア抑留は、長らく日本人の兵士だけのものと考えられてきたが、ソ連に抑留されたのは、日本人だけではなかった。本書は、ドイツ人の捕虜問題を扱い、シベリア抑留研究の世界的広がりと世界的な研究の視点を提示した。これまで日本人抑留者の回想等ではドイツ人抑留者について触れていたものはあったが、問題を全体的に俯瞰したものはなかった。
ドイツ人のソ連抑留の前に、ナチス・ドイツのソ連人捕虜の扱いについて本書は触れている。大量銃殺、石炭産業等での使役、疫病の蔓延、大量の餓死者等と、まさに過酷な状況だったことがわかる。ソ連人捕虜達はソ連国内では「祖国への裏切者」と見なされ、解放後も様々な懲罰的扱いを受けたのである。
スターリングラード戦以降ドイツ人捕虜の問題が本格化し、戦後復興にとって必要不可欠な労働力としてドイツとその同盟国の捕虜が使役された。また軍人だけではなく、非軍属の民間人、女性達も抑留することがあらかじめ決められていた。まさに、抑留が「人的賠償」に名を借りた報復だったことを本書は示した。ドイツ人の抑留と日本人の抑留との比較という視点を広く知らしめたことは本書の功績といえるだろう。本書のドイツ人抑留者の生活に関する言及は、健康状態、食糧状態(特に給食基準表で示している)、労働時間、サボタージュ、心理精神状態、娯楽・文化活動等、多岐に及んでいる(日本人抑留についてもあらゆる方面から考察していることはいうまでもない)。
だが枢軸側に立って東部戦線に兵力を送り込んだのは、ドイツだけではなかった。イタリア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、フィンランド、さらにはスペインも。本書がこれらのソ連抑留問題に触れていないのは非常に残念である。もちろん、ドイツに比べ研究が進んでいないという現状ではあるが、これから光が当てられることは間違いない。
比較の問題で触れなければならないのは、反ファシスト民主化運動の名を借りた共産主義的政治教育である。日本人の場合、民主化啓蒙活動のための新聞である『日本新聞』が創刊され、「シベリア天皇」とあだ名される人物が登場し、各所で階級章撤廃等の様々な運動に発展する。ドイツ人捕虜の場合は、自由ドイツ国民委員会、ドイツ将校連盟の結成と、機関誌『自由ドイツ』、そして自由ドイツ国民委員会放送へと展開した。これら捕虜に対する反ファシスト民主化運動は、第一次世界大戦から世界の共産主義革命運動を指導してきたコミンテルンの中で編み出されたものである(本書ではコミンテルンの説明がない)。コミンテルン幹部の一人であるマヌイリスキー等が主導する形で、反ファシスト民主化運動の検討が進められ、コミンテルン解散後はソ連共産党中央委員会の中に第99研究所が作られ、運動の継続推進が任される。
ドイツ人抑留者による反ファシスト運動は、ソ連当局がコントロールできないほどの独自路線を歩みはじめ、やがてそれがソ連にとって疎ましい存在となり、戦後は親ソ的なものにとって代わられる。収容所でのスターリン感謝等は日本のものと似ている。日本人もドイツ人の回想でも、たとえソヴェト民主主義だとしても、収容所を初めて民主主義に触れた場だと評価していることは面白い。
日本人の抑留に関していえば、前述した兵士だけではなく、非軍属の官吏や満鉄職員・技術者等の民間人、看護師等の女性達や、さらには朝鮮人の抑留もあった。特に本書は、北朝鮮、樺太での現地抑留の問題に触れている。接収した企業を操業するために旧従業員の日本人が使役されたが島ぐるみの留用の樺太と日本人退去方針の北朝鮮の違いがあった。これらの問題はまさに「忘却」され語られることがなかったが、抑留問題の中に組み込み、検討しなければならないという姿勢が本書には見られる。日本人抑留者には、ソ連国内の刑法を犯した犯罪者や戦犯・政治犯として処罰された者達もいた。その多くが無実の罪であった(中には中村百合子のようなスパイもいた)。こうした者達にも本書の考察は及んでいる。つまり、シベリア抑留を総合的にとらえているのである。さらには、抑留者達によって「異国の丘」等の歌や短歌、俳句、川柳等が作られ、抑留者達が残したものが非常に価値のあるものであることを明らかにし、それらを紹介することで、抑留者の心に触れようとしている。
本書は、抑留におけるソ連国内事情も明らかにしている。例えば外圧により送還を求められたソ連中央指導部と、まだまだ復興に抑留者達を使役させたい地方指導部との対立の問題である。さらには収容所長等の係官が捕虜経験者で降格後配置されたこと、国防省管轄の独立労働大隊、つまりは捕虜の労働組織を軍隊編成と同様のものとし、軍関連のインフラ整備に使役した組織があり、そのソ連人幹部の一部が捕虜経験者だったことも。
総じて本書は、縦軸としての歴史的経緯、横軸としての世界的広がりを据えて、日本人抑留者達が個々に経験したこと、記憶の断片をつなぎあわせて、抑留問題の全体像を浮かび上がらせ、それに歴史的・世界的意味を与えたといえるだろう。そういった作業の積み重ねが本書に結実されたのである。
しまだ・あきら
1965年横浜市生まれ。法政大学文学部史学科卒業、一橋大大学院社会学研究科博士後期課程修了。ロシアの声放送(旧モスクワ放送、現ラジオ・スプートニク)日本語課翻訳員兼アナウンサーを経て、関東学院大学経済学部講師。博士(社会学)。専門は歴史学、国際関係論。著書に『ソ連・コミンテルンとスペイン内戦』(れんが書房新社)、『コミンテルンが描いたユートピア』(図書新聞)など。最近の論文に「木村慶一―シベリア抑留者の便りを伝えた男」(『ユーラシア研究』No.54)、「第二次世界大戦中のモスクワ放送―モスクワからの日本語放送はいかにして開始されたのか」(『早稲田大学アジア太平洋討究』第27号)など。
この一冊
- 『シベリア抑留―スターリン独裁下、「収容所群島」の実像』関東学院大学経済学部講師/島田 顕
- 『琉球独立への本標-この111冊に見る日本の非道』辺野古リレー 辺野古のたたかいを全国へ/岩川 藍
