この一冊
『戦後日本の反戦・平和と「戦没者」:遺族運動の展開と三好十郎の警鐘』(今井勇著 御茶の水書房、2017.8)
私たちの内に潜む反戦・平和の敵
安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京 事務局長 新 孝一
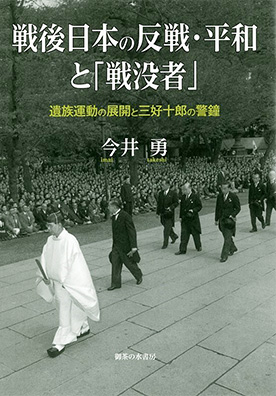
◆戦後日本の課題を明確化する「戦没者」
評者は、反天皇制運動に参加して、毎年8月15日には「全国戦没者追悼式反対・靖国解体」を掲げた集会とデモに取り組み、また、2013年12月の安倍首相の靖国神社参拝違憲訴訟の原告団事務局も担っているものである。
その意味では、本書で問われている「戦没者」および遺族、国家による戦争の死者の「慰霊・追悼」といった問題については「実践的関心」を持ち続けているひとりである。しかし「実践的」というと、ともすれば課題とする対象を、往々にして単純化して理解してすます傾向に陥りがちだ。そうしたことをなるべく回避していくためには、そこで立てられた問いの前で、いったん立ち止まることが必要と思うが、立ち止まるためには、そこに問われるべき問いがあるということ自体を、まずは発見していかなければならない。運動史に関する研究が持つ意義とは、第一にそうしたものの提示であるべきだろう。
この点で本書は、そうした期待に充分応えるものであった。本書において、私たちが立ちどまるべき課題は、本書の書名に示されているとおりだ。
まず、戦後日本の反戦・平和と「戦没者」、その関係性について。戦争によって生み出された死者の存在が、戦後日本の反戦・平和意識の基底にあったことは確かであり、それは政治的立場を超えて繰り返されるクリシェとさえいえる。次に遺族運動とそれとの関係。ここで分析されている遺族運動は、日本遺族会の運動へと集約されていくそれだが、以前ほどの力は失っているとはいえ、日本遺族会は、日本会議にもつながる改憲・靖国派の右派勢力そのものである。「戦没者」を介してつながる「平和」と「遺族運動」をめぐる関係性は輻輳している。
そして三好十郎。彼の名は、私も参加していた90年代後半の反派兵グループのなかで、「テロにも反テロ戦争にも反対」という文脈で、その「絶対平和主義」について言及されていた。その三好の平和主義の根底には「戦没者」と遺族とが据えられていると著者は指摘する。これら「反戦・平和」「戦没者」「遺族運動」「三好十郎」というそれぞれの項は、必ずしも自明の存在としてあるわけではない。そして何より、それらを成り立たせている場としての「戦後日本」のありかたこそが、この本において問われている。
あらかじめ言っておけば、著者の立場性ははっきりしている。そもそも、三好十郎を大きく取り上げるところに、著者の「反戦・平和」にたいする基準が見て取れるはずだ。その鮮明な問題意識の表明は、最近の運動史・社会史研究に往々にして見られる、実証的に詳細なデータを渉猟し、それ自体興味深く重要な対象を扱いながら、しかしそこで明らかにされる事実に対する著者のスタンスが一向にはっきりしない傾向とは一線を画している。にもかかわらず、歴史学者の手つきといえばそれまでかもしれないが、著者は結論を急がない。
たとえば「反戦・平和」というものについて、私は最初、なにかその言葉が宙吊りになったまま、議論が進んでいるような感覚をおぼえた。しかし読み進めるにつれ、そこで論じられている「反戦・平和」がまさしく、こうした不分明な姿で存在していたのではないかと考え直させられた。本書の記述の中心は、遺族運動の言説分析であるが、その論理を内在的に追っていくことで、別にありえた可能性が随所で垣間見られる。そう考えると、安倍の言う「平和」でさえ、それは単なる虚偽であるというより、戦後日本における「平和」の問題系の内部に属するというふうに考えるべきではないか(もちろん、別の「可能性」ではなく、その「平和」の不可能性を照らし出しているという意味でだが)。
◆作為された「戦没者」像と解体された「平和」論理
著者によれば、この本の課題は、「敗戦とその後の占領政策にともなう強い喪失感の中から形成された戦没者遺族運動」を対象として、「自己表象としての戦没者遺族像の模索と並行しながら、運動そのものの求心力として求めた『戦没者』像の再評価過程を分析」し、「その批判的検証を通じて、平和憲法体制下の戦後日本における反戦・平和の実相を明らかにする」ことにある。本書の冒頭でも述べられているように、この「戦後日本の反戦・平和」とは、保守と革新を問わずアプリオリに共有されていたが、事実上解体されてしまっている。そのことを、「『戦没者』像の再評価」と関わらせて解明していこうというのだ。
そもそも「戦没者」とは何か。戦没者に「 」が付いているのは、それが個別の戦争の死者をさすのではなくて、「広く国民が共有することになる没個性的な集合体イメージ」をさすからである、という。個々の戦没者とは別物だ。それはごく一般的には「国家のために尊い生命を捧げ、平和国家建設の礎となった」とされる存在であるが、そうした「戦没者」像自体が作為的なものであった。
著者によれば、「戦没者」=戦争の犠牲者というときの「犠牲」の論理が、実は「受難的犠牲と貢献的犠牲」との側面に分けられ、遺族運動の歴史においては、その両者が一体となって「使い分けられていた」ものから、はっきりと後者へと重点を移し、その「殉国」的側面が強調されるようになっていった。しかしながら、遺族運動によって示される「戦没者」像においては、常に「平和」への言及も失われることはなく、加えて民主主義との結びつきも強調されるようになるという特徴がある。そこでまた、「犠牲」の意味の多様性や、「平和」の論理そのものが解体されてしまう過程も存在することになっていく。
「戦没者」について、実は法的に確定した定義は存在していない。日本遺族会が再編・再評価の必要性を求め続けてきた「戦没者」とは、戦病死した軍人・軍属・準軍属に限られ、つまりは戦争死没者である空襲などによる戦災死者や原爆犠牲者とは明確に区別されるものだった。それは「国との雇用関係」の有無によって区別される、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(それは同時に、靖国神社合祀の基準ともなった)の対象とも重なる。
こうして、遺族会的「戦没者」は、国への特別な貢献によって、ある種「特権化」された存在となる。それは「死の序列化」であり、また、戦争の死者に対して、本来国がなすべきだった賠償を、報奨ヘとすりかえていく論理立てとして、私たちも批判してきた。しかし著者は、それだけではなく、こうした論議立てが、「本来、『戦争による犠牲を再び繰り返さない』ための運動であることを自認する遺族運動が、国家のために尊い生命を捧げた『戦没者』の貢献的犠牲を顕彰・継承しようとする」という、それまで遺族の内部に確実に存在していた反戦・平和論理との「決定的な矛盾さえ生じさせかねない」ものであったことに着目する。
そこで、「反戦・平和を基調とする平和憲法体制下において、国家のために尊い命を捧げた『戦没者』が、いかにして国民的な支持を得るに相応しい存在であるかを明らかにする」ことが遺族会の課題となる。つまり、「殉国」のイデオロギーだけでは意義づけしきれない部分を「平和」と接合してその死を評価する論理が必要とされたということだ。
◆「戦没者」、象徴天皇制、そして沖縄
具体的な遺族運動の展開については、第1章から第4章を通じて具体的に描かれる。それは、それぞれの章のタイトルにあるように「戦没者遺族運動の出発と戦後国家への志向」「犠牲者=受難者としての『戦没者』と反戦・平和」「受難者から貢献者へと転換する『戦没者』」「戦没者遺族の世代間格差克服の試みと英霊精神の再生」という筋道をたどった。その展開を通して、「平和の礎」としての「戦没者」の位置づけが確定され、そのことによって「顕彰」されるべき「英霊」となり、さらには具体的な戦争の評価からも切り離されて、「身命を挺して難局に当たった象徴」として純化される。「戦後日本が享受する既存の平和、民主主義」を守るためにこそ「英霊精神が求められる」といった、いわば「もうひとつの」平和と民主主義=国民運動としての英霊精神継承運動へと展開していく姿が描き出されているのだ。
私自身の関心から言えば、この遺族運動のなかで天皇の存在が果たした役割がある。「民主戦線」の一翼であることを志向した初期遺族運動から脱却していく上で、「戦前・戦後の価値観を結びつける唯一の紐帯」たるその存在において天皇が果たした役割は大きかった。その価値観の連続が、天皇によって「象徴」された。それは主に、50年代の昭和天皇についてだが、その後の「平和と民主主義」に適合する遺族運動という流れからすれば、現在の「平和天皇・明仁」においても、その役割は無関係ではないはずである。
こうした「平和」のありようについて、第5章の「兵士・戦没者・遺族をめぐる劇作家三好十郎の視線」が、別の角度から考察を加えている。三好が批判したのは「平和への願いを高唱しながら、明確な反戦の意思を示さず、国家への献身意識を否定することのできない」同時代の保革両陣営のあり方であった。つまり、保守も革新も共有していた「『国家への献身』、『国のため』という意識の無批判な受容こそが、再評価された『戦没者』像において反戦や戦争放棄の明確化を挫折させる決定的な要因となった」。それは反戦を欠落させた「平和」であるとともに、国家に親和的である「平和」に対する痛撃にほかならなかった。こうして、「戦後日本の反戦・平和」が自らの課題として直面しなければならない「国家」という存在が前面化してくる。
終章で紹介されている、もうひとつの遺族運動=キリスト者遺族会から平和遺族会へと繋がっていく流れこそが、「国家を対象化する(遺族の)運動」であった。重要なのはそこで、これまで一貫して「没個性化された『英霊』としての『戦没者』」であった存在が、「それぞれ『殺し・殺される』兵士であったことを自覚」することで「画一化された英霊顕彰運動からの脱却」を果すものとなったという指摘だ。ここで私たちは、まず、集合化された「戦没者」が個々の戦没者として捉え直されなければならないこと、そのことがもたらす可能性を知ることになる。
このことと関連して、私は沖縄における「戦没者」と遺族運動をめぐる問題群を想起しないわけにはいかない。「鉄の暴風」という凄惨な地上戦が生み出した「戦没者」と「遺族」のありようは、「本土」のそれとは大きく違っていたはずだ。だが沖縄においても、「援護法」がその展開を押しつぶす役割を果していただろう。
本書においては沖縄の遺族運動にふれられていないが、それは「戦後日本」という枠内に包摂されるべきではないという問いに関わっているのかもしれない。いずれにせよ、「積極的平和主義」「安全保障法制」のもとで新たな「戦没者」が生み出されかねない現在において、事態はなお進行形であり、「国のために死ぬ」ことの肯定がもたらす「戦後日本」の行き着いた現在と、個々の死者に繋がる人びとが示す抵抗のありかについて、考えていくべき課題は多い。
しん・こういち
1959年生まれ。横浜市立大学文理学部卒。出版社勤務のかたわら、1980年代後半から、反天皇制運動に参加。安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京事務局長。
この一冊
- 『戦後日本の反戦・平和と「戦没者」:遺族運動の展開と三好十郎の警鐘』安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京 事務局長/新 孝一
